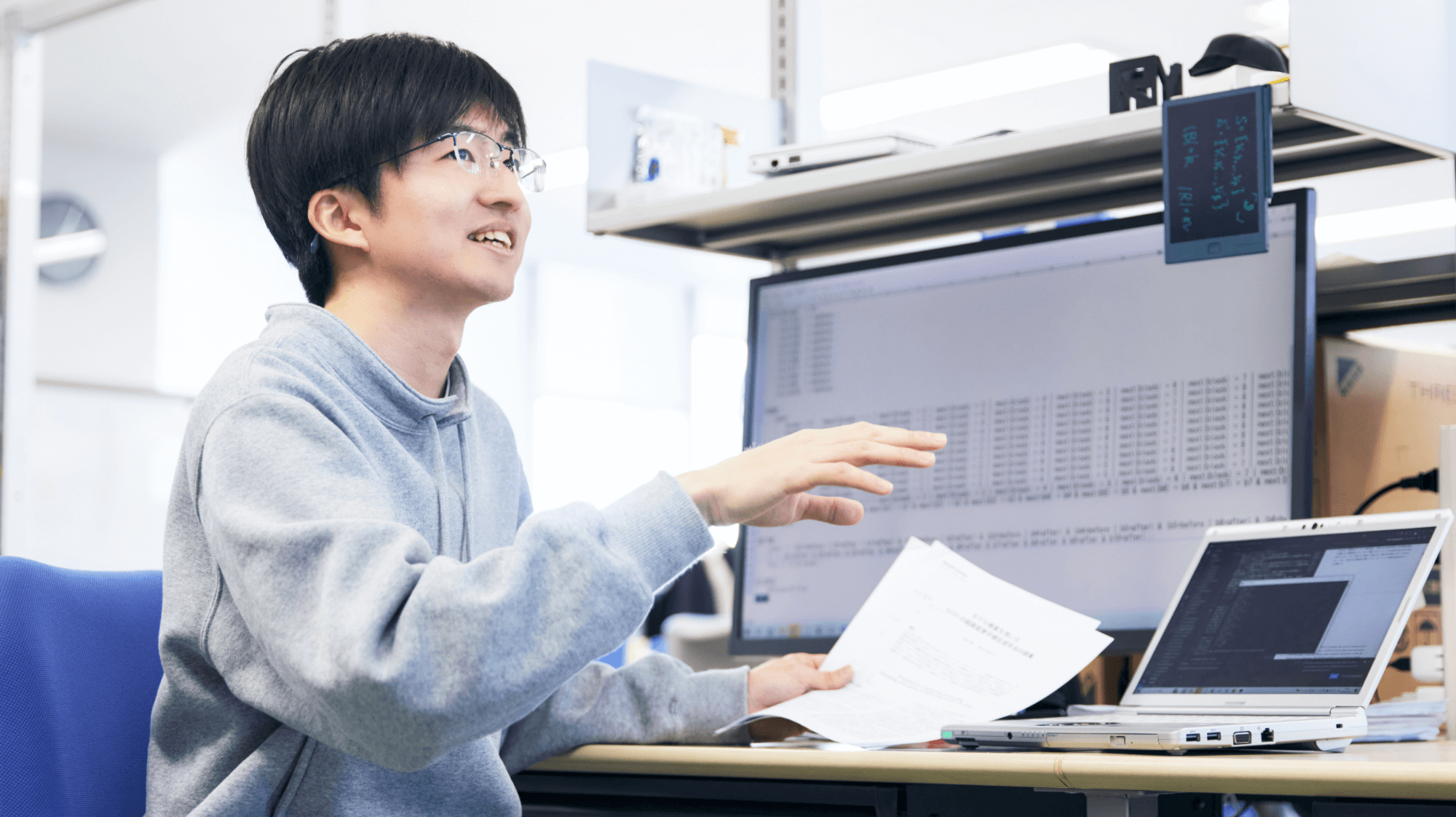自分が選ぶ研究領域のスペシャリストになってください。 ⼯学研究科 情報学専攻 情報システムデザイン専修
知能ロボット研究室
MASATOMO KOBAYASHI
小林 政智 内定先 野村総合研究所(NRI)/ NRI Digital-
ー関東学院大学をなぜ選んだか、きっかけや理由を教えて下さい。
父の方針で幼い頃からパソコンに慣れ親しむ環境で育ち、小中学生の頃は、ゲームや身近な機械をどのような仕組みで動いているかを分解して理解する遊びが好きでした。情報学系の分野に進路を定めたのは、「りんな」や「α碁」のようなAI(人工知能)の進化を身近に感じることが多くなり、その無限大の可能性を専門的に学んでみたいという気持ちが強くなったからです。進学の際は、総合大学という強みを活かして理系文系問わず、サークルなどの課外活動を通じて、様々な人との交流ができる点を重視していました。
-
ー現在、どんな研究をされていますか。また、研究の魅力などを教えてください。
沿岸部の深夜などの密漁が行われやすい時間・場所をドローンで自律飛行し、そのドローンが取得した赤外線画像および位置情報から怪しい物体(人・車・船・ダイバーの泡)とその物体位置を特定し、関係者に通報するシステムの研究開発をしています。プログラミングコードの改善など、検出精度を高めるために改善点を1つずつ洗い出してうまく解決できた時は、まるでパズルを解くような面白さと達成感が味わえます。また、RPGのように様々な人と関わりあって助け合い、経験値を高め、仲間を見つけていく過程も、研究の面白さ、魅力の一つかなと思います。教師データを作る際に、同じような作業が続いてしまうのが少し大変ですが、単調な作業も計画を建てて目標に向けておこなったり、好きな音楽を聴きながら作業をするなどしてゲームのように進めて乗り越えてきました。
-
ー大学・大学院で得た学びは、社会に出てどのような場面で活かしたいですか。
大学院での研究活動を通して、ものごとを多角的に捉える視点を身につけることができました。研究では特定の問題に対して深く掘り下げつつも、さまざまな可能性を考慮し、異なる視点やアプローチを組み合わせる必要がありました。この経験から、課題解決において柔軟かつ論理的に考える力が養われました。また、研究に伴うスケジュール管理や日程調整、進捗報告などのメール対応を通じて、効率的に業務を進めるための実務スキルも磨かれました。特に、限られた時間で複数のタスクを並行して進める力は、社会人として重要な能力だと感じています。社会に出てからは、これらの能力を活かし、複雑なプロジェクトを適切にマネジメントしながら、チームで協力して成果を生み出せるよう努力していきたいです。また、視野の広さを活かして、さまざまな立場の人々と円滑にコミュニケーションを図り、信頼関係を築いていくことも心がけていきたいと思います。
先輩の声 SENIOR’S VOICE
一覧はこちら