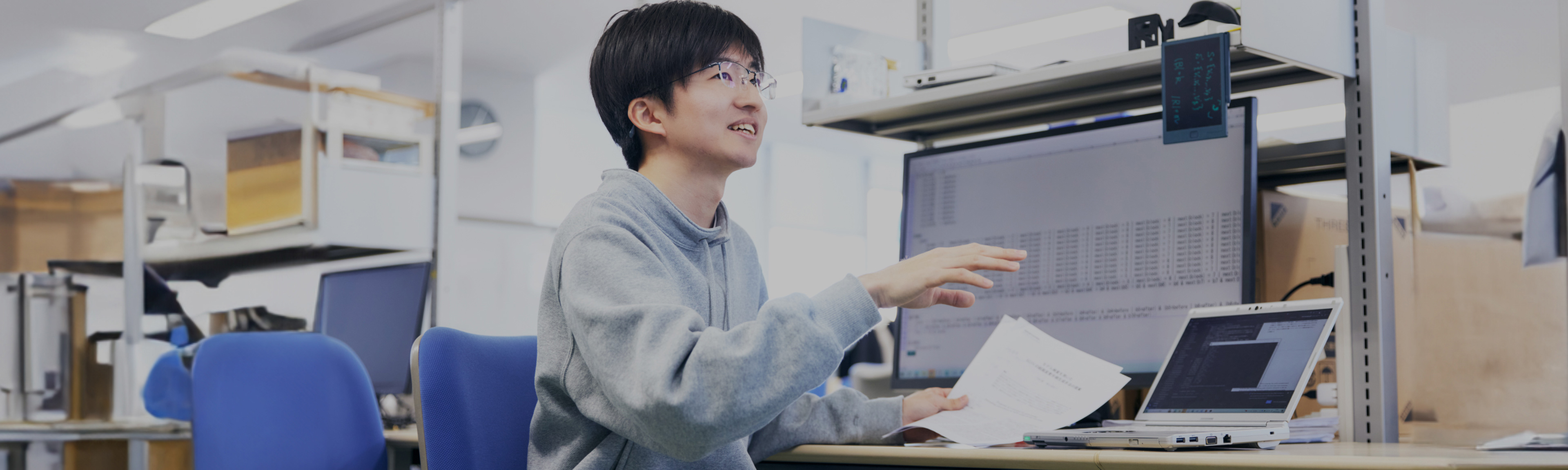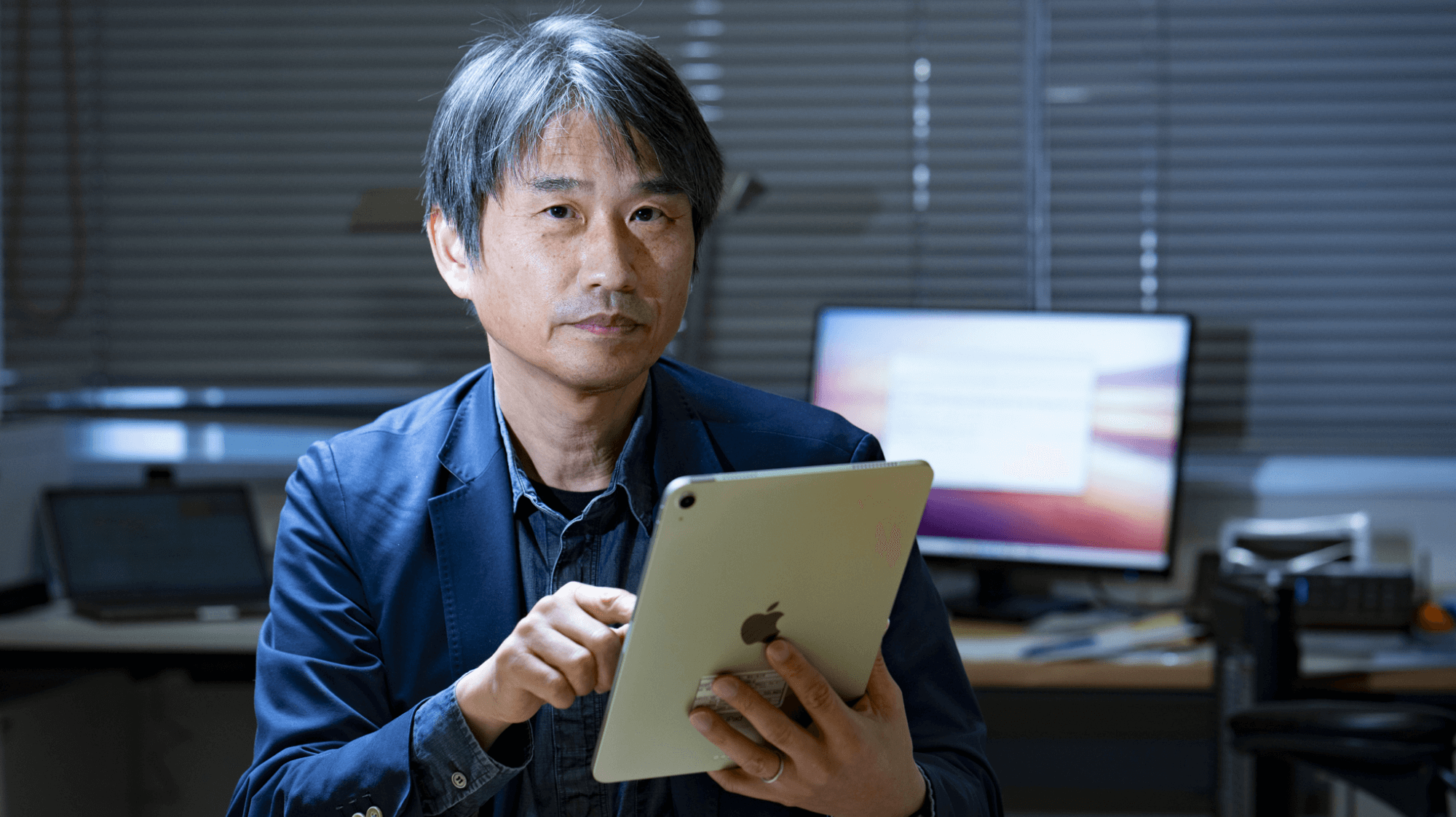
AIが⼈間にとって本当の意味での“⼈⽣のパートナー”になる未来のために
YOSHIKAWA ATSUSHI-
背景
話しやすさという側⾯から、⼈間とAIの⾃然な付き合い⽅
ができないか近年は、AI(⼈⼯知能)を活⽤したChatGPTが⼀般化するなど、以前にも増して⼈間とコンピュータの距離が接近しつつあると感じます。特に⼤規模⾔語モデルの発展は著しく、近いうちに⼈間と対話するAIが登場することは予測をしていました。そこで私は、AIに対しての「話しやすさ」という⾯からアプローチしてみようと考え、研究に取り組んでいます。
例えば、⼈間同⼠で会話する場合、相⼿の外⾒や⼝調、話題の提⽰⽅法などによって話しやすさが⼤きく変わりますよね。そうしたデータをAIにインプットすることで、より⾃然な付き合い⽅ができるのではないかと捉え、研究を⾏っている次第です。 -
目的
何気ない会話のなかにある、重要な情報を読み解いていく
ー例えば患者さんとの会話の余談から、薬の相性を読み解くことお医者さんは多忙なお仕事なので、患者さんとの雑談になかなか時間を避けられないこともしばしばあるかと思います。しかし、何気ない会話のなかに重要な情報が隠されていることもまた事実。家族の既往歴が話題に出れば、そこから遺伝的に薬の相性を読み解くことも可能なわけです。そこで、ときにはAIが雑談しながら、なるべく患者さんに負担をかけないように⾃由な会話を促して、情報を読み解いていくチャットボットを制作しました。
-
提案手法
意図的に雑談を交えて、話しやすさを演出する。
すでに開発したチャットボットを内蔵したタブレットを、埼⽟県内の⻭科医院で試験利⽤させていただいています。これはテキストで対話しながら診療に必要な情報を深掘りする仕組みのものです。従来のAIは患者さんの回答に対して簡潔に返答しますが、このチャットボットは意図的に雑談を交えるよう調整されていて、より⾃然な付き合い⽅ができるようになっています。
-
検証
より⼈とAIが話しやすくなるように、⼈の⾒
た⽬も考慮した話し⼿に利⽤してくださる⽅の⼼理的抵抗感の払拭をめざして、よりAIに親しみやすさを抱いてもらうため、対話の相⼿となる⽅の外⾒的特徴についても研究を進めています。男の⼈か⼥の⼈か、若い⽅かご年配の⽅か。こうした属性によっても話しやすさに差が⽣じるのかと思うので、その⼈それぞれに合った話ができるAIを⽬指しています。
-
まとめ・効果
⼈間と同じようにAIと世間話ができる、豊かな未来を⽬指して
データは⾮常に有⽤ですが、そのままを反映してしまえば偏った⾒⽅になったり、対象の⽅の⾒た⽬によっては、⼼ない⾔葉をAIが投げかけたりする可能性もあります。それは対等な関係性を築いたとは呼べません。私が⽬指すのは、⼈間と同じようにAIと世間話ができる、豊かな未来です。この未来の実現のために、より⼀層技術を向上させて⾏きたいと考えています。
SITE CONTENTS